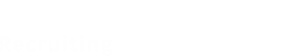インタビュー上席研究員 川口 宗紀
INTERVIEW03
若手が確たる専門領域を軸に研究ができる環境がある
川口 宗紀
上席研究員
2003年新卒入社

インタビュー
様々な挑戦ができると思った
私は、大企業で働くよりも、規模としては小さい会社の方がいろいろなことに挑戦できるだろうし、自分の性に合っていると感じていたため、インターンシップでお世話になったMTECに入社しました。
大学では応用数理を専攻し、大学院では応用数理の中でも実学的色合いの強い金融工学の研究室を選んだのですが、その指導教授がMTEC出身だったことがきっかけとなり、インターンシップに応募しました。そのとき経験した業務が自分の興味に合致するものだったため、ここで研究に没頭したいと思うようになりました。

研究者育成もリーダーの責務
7年前に「主任研究員」となり、研究と同時にプロジェクトのリーダーを任されるようになりました。リーダーになると、お客様との折衝やスケジュール管理が大きな比重を占めるようになり、お客様が私たちにどう動いてほしいと考えているのかをきちんと拾い上げて、それをメンバーに伝え、プロジェクト全体をその方向に動かしていくことに腐心することになります。大変ではありますが、研究以外の部分で充実感を味わえるのは嬉しい点と言えます。
また、若い研究者の育成も責務の一つです。分析対象に対する理解であったり、分析の際の道具立てであったり、研究の勘所をつかむためには、経験を積んでいくしかありません。そうした点にも配慮して、メンバーの研究を見守ったり、ときにはアドバイスを送ったりしています。ただ、私たちの場合、確たる専門領域があって、そこを軸に仕事をしていますから、専門外のことでお客様から注文が付くことはあまりありません。その意味で、若い研究者にとっては、外部要因に惑わされず自分の得意なことに集中して仕事ができる、良い環境になっていると思います。
会社の支援で博士号を取得
私は会社から支援を受けて、博士号を取得しています。仕事と大学院通いの両立は苦労しましたが、その苦労に見合うだけの自信を持つことができたので、この決断は間違っていなかったと確信しています。博士号は、目先の業務にすぐに役立つわけではありません。しかし、この選択が自身を成長させることができただけでなく、働きながら自分を磨く姿を若い研究員が見て一つの目標にしてもらえたとすれば、本当に価値のある挑戦になったのではないかと思います。
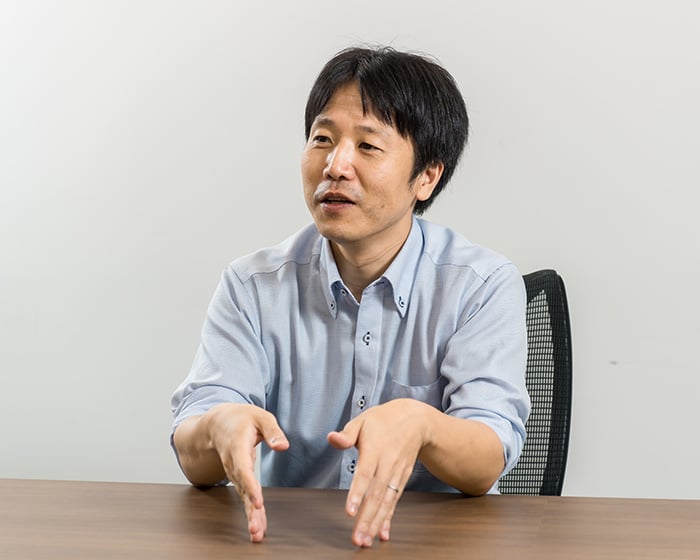
携わったプロジェクト
株式売買のより精緻な分析
現在、私は半期を一区切りに複数のプロジェクトを同時に進行させています。その一つである「株式売買のより精緻な分析」に関する研究プロジェクトは、個人的に大変興味深く、大いにやりがいを感じている業務です。このプロジェクトは、アルゴリズムトレーディングに関する研究で、3年前から立ち上がっていました。当初は社内研究という色合いが強く、論文や報告書などの形で成果を発表するだけだったのですが、今年度からは実際に現場で使うことを前提にした段階に進んでいます。扱うデータ量が膨大で、いろいろなスキルを組み合わせて分析していく必要があるため、かなりやりごたえがあります。また、いろいろな方に関わってもらっているので、その方たちがうまくシナジーを生めるように誘導していきながらプロジェクトを回していくということも、私にとっては新鮮で面白みを感じています。

半年プロジェクトの流れ
-
1ヶ月目
プロジェクト始動
キックオフミーティングから始まり、研究課題の確認、研究方針の策定などを行う。
-
2ヶ月目
基礎調査
様々なデータから活用できるものをしっかり見極め、プロジェクトの地盤を固めていく期間。手を動かしていく中で理解が深まるとアイデアがいくつも浮かんでくる。
-
3ヶ月目
モデルの策定
基礎調査のデータの性質から鍵となる部分を選出し、ベースとなるモデルを策定していく。
-
4〜5ヶ月目
モデルのブラッシュアップ
簡単なモデルを作ることから始まり、トライ&エラーでモデルをブラッシュアップしていく。様々なアイデアが加味され個性を持ったモデルがいくつも誕生するため、研究者にとっては面白さややりがいを感じる期間。
-
6ヶ月目
成果のまとめ
ブラッシュアップ期に出来上がった個性に富んだモデルから最適解を選びだし最終形に。
メッセージ
あらゆることにハマれる力を
MTECには、個人個人がしっかり個性やスキルを発揮しながら、時に協力したり、時にライバルになったりしながら成長していける環境がありますし、そうあってほしいと思っています。MTECへの就職を志望する方々は、すでに基本的なスキルや専門性を身につけていらっしゃると思いますので、自信を持ってトライしていただければ嬉しいです。
その個性に+αであるといいなと思うのが、「自分の興味に正直になれる力」や「あらゆることにハマれる力」。この力があると研究者として伸びていけるし、成果もついてくるはずです。